食欲不振
食欲不振は投与開始後1~2週目の投与早期から発現します。一般に食欲不振は他の副作用に随伴して起こることが多く、悪心・嘔吐、下痢、便秘、腹部膨満感などの消化器症状によるもののほか、味覚・嗅覚異常、全身倦怠感、精神的な原因によることも考えられます。食欲不振が発現した場合には遷延化させないために、それぞれの原因に対して早期から対策を講じる必要があります。また、食事そのものについても工夫が必要で、食べやすい食事を用意するのはもちろん、気分の良いときに食べることが出来るように、いつでも食べられる用意をしておくなどの工夫も重要です。
発現率
ティーエスワンの承認時までの臨床試験、使用成績調査及び市販後臨床試験における食欲不振の発現率は下表のとおりでした。単独投与に比べ、CDDP(シスプラチン)併用投与で発現率が著明に増加しています。
| 副作用 | 承認時までの臨床試験 | 使用成績調査(単独投与+併用投与) | 市販後臨床試験 (胃癌:SPIRITS) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単独投与 (751例) |
CDDP併用投与 (55例) |
胃癌 (3,808例) |
頭頸部癌 (375例) |
非小細胞肺癌 (1,669例) |
単独投与 (150例) |
CDDP併用投与 (148例) |
|
| 食欲不振 | 281例(37.4%) | 43例 (78.2%) |
1004例(26.4%) | 121例(32.3%) | 250例(15.0%) | 55例 (36.7%) |
107例 (72.3%) |
発現時期
胃癌のティーエスワン使用成績調査では、投与1~2週目が最も発現が多く、投与開始後4週間以内に全体(n=1,004例)の71%の発現がみられ、初発までの期間の中央値は13日(n=764例)でした。一方、後期臨床第Ⅱ相試験での初発までの期間の中央値は14日(1~244日)(n=168例)でした。
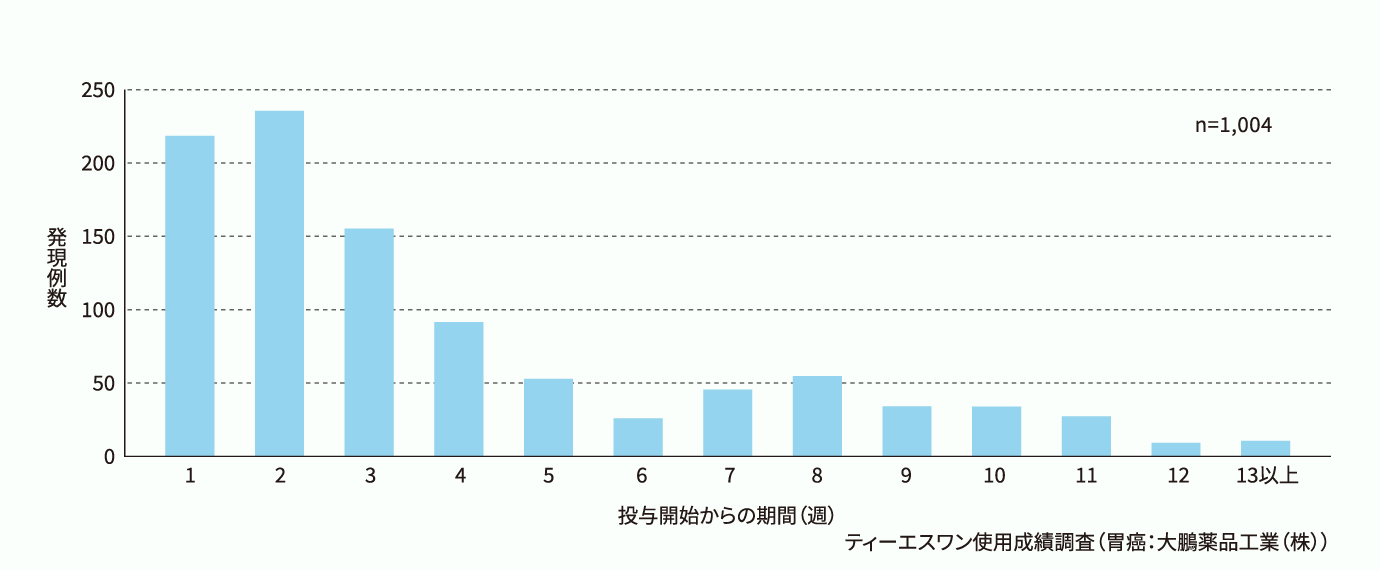
処置
エスワンタイホウの休薬や減量、ならびに悪心・嘔吐などの原因症状に対する処置が中心となります。悪心・嘔吐には制吐作用を有する薬剤投与、下痢には止瀉剤や整腸剤、その他を投与します。また、短期にステロイド剤投与を行う場合もあります。なお、食事に関しても工夫することが重要です。
転帰
胃癌のティーエスワン使用成績調査での食欲不振発現例のうち、回復・軽快は72.3%にみられ、回復・軽快までの期間の中央値は16日(n=764例)でした。また、後期臨床第Ⅱ相試験における最高グレード発現から消失までの日数の中央値は14日(1-140日)(n=135例)でした。
| 食欲不振 | 発現例数 | 回復・軽快 | 未回復 | 不明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用成績調査 | 胃癌 | 1,004例 (26.4%) |
72.3% | 27.0% | 0.7% |
| 頭頸部癌 | 121例 (32.3%) |
89.3% | 9.1% | 1.7% | |
| 非小細胞肺癌 | 250例 (15.0%) |
84.0% | 14.8% | 1.2% | |
(調査票回収時の転帰)
対策
参考
症状をおさえるための工夫
- 食欲不振の原因が明らかであれば、それを改善する工夫をする。
- 気分の良いときを選んで食べられるものを食べる。
- 気分転換をはかり、気分よく食卓につけるようにする。
症状が現れたときの対策
- 食べられそうなものを、いつでも食べられるよう用意する。
- 食欲をそそるような盛りつけや食卓の雰囲気を心がける。
- 消化がよく、栄養価の高い食品を選ぶ。
症状別・生活と食事のくふう「 がん患者さんと家族のための抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 改訂版」
(山口 建 監修:女子栄養大学出版部)pp129-137, 2018 より抜粋
継続投与・再投与
食欲不振が遷延化すると栄養不良や体重減少を引き起こし体力も低下するため、食事の工夫などの対策を講じて食事をとるようにすることが重要となります。そのため、原因に対する対処を行うとともに服薬指導に食事の工夫を取り入れることも重要です。

